令和7年度 施政運営方針
令和7年度 施政運営方針 (PDFファイル: 365.3KB)
はじめに
令和7年河南町議会3月定例会議の開議にあたりまして、令和7年度の町政運営と施策に関する基本的な考え方をご説明申し上げ、住民並びに町議会の皆さんのご理解とご協力を賜りたく存じます。
住民の皆さまからの温かいご支援とご信託により、2期目の町政を担わせていただき、1年が経過しようとしております。皆さまのご期待を背に、重責を感じながらも、一歩ずつ前進してまいりました。
我が国は、かつて経験したことのないスピードで少子高齢化と人口減少が進んでおります。令和6年の人口動態統計速報によると出生数は過去最少の72万人となり、働き手の減少による労働力不足が深刻な課題となっています。あわせて、長寿化が進む中で、医療や介護、福祉のあり方も問われています。
また、東京圏への一極集中が進む中、その流れを変える「地方創生2.0」への取り組みが進められるとともに、物価高騰やエネルギー問題、デジタル技術の進展など、社会経済の変化が私たちの暮らしや地域経済にも大きな影響を及ぼしております。
こうした状況の中、地方自治体の果たすべき役割は、ますます重要となってきております。今こそ、地域の力が試される時代であり、住民の皆さまとともに、よりよい未来を築いてまいりたいと存じます。
河南町におきましても、少子高齢化への対応を最重要課題と捉え、子育て支援や福祉・医療体制の充実、そして、住みやすい環境の整備に力を注いでまいります。あわせて、デジタルトランスフォーメーション(DX)を活用した行政の効率化などにも取り組み、持続可能なまちづくりを推進してまいります。
本年1月17日には、阪神・淡路大震災から30年が経過いたしました。当時の被災状況が報道される映像から、我が河南町においても被災地支援を行ったことを思い出します。このような大地震の怖さを痛感し、30年以内に80%程度の確率で発生が予想される南海トラフ地震への備えも必要となってまいります。
そのためにも、地域コミュニティの役割もこれまで以上に重要となっております。少子高齢化が進む中で、住民同士の支え合いや地域のつながりを深めることが大変意義深いものであります。行政としても、地域の皆さまの自主的な活動を支援し、共に歩んでまいりたいと考えております。
今後の行財政運営につきましては、大阪府、太子町及び千早赤阪村の2町1村未来協議会における議論をさらに深め、広域連携の取り組みや合併について調査・検討を行ってまいります。
いよいよ4月13日には「大阪・関西万博」が開幕いたします。この歴史的な機会に、河南町の特色を全国へ発信し、多くの方々に魅力を知っていただけるよう取り組んでまいります。町のブランド力を高めるため、町の特産品であるイチゴやイチジクなどを活用したイベントや商品開発にも力を入れ、観光振興や地域産業の発展につなげていきたいと考えております。
住民の皆さまと共に、活気あふれるまちづくりに努めてまいりますので、引き続きご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
令和7年度予算の総額でございますが、
一般会計が 76億4,036万8千円
下水道事業会計を含む特別会計が 47億1,145万円
合 計 123億5,181万8千円であります。
また、令和6年度6月補正後予算で比較しますと、一般会計で8億5,537万1千円の増、下水道を含めた特別会計は、1億1,544万5千円の減で、合計では7億3,992万6千円の増であります。
令和7年度一般会計予算の歳入でございますが、
町税は、前年度と比較いたしまして、1億20万6千円の増を見込んでおります。
個人住民税は、給与所得等の上昇に加え、定額減税が終了したことにより、大幅な増を見込むとともに、法人町民税も増を見込んでおります。固定資産税は、新築家屋の増や法人の設備投資に伴う償却資産の増、町たばこ税の売り渡し本数の増などにより、町税全体としては、増額となりました。
一方、地方特例交付金につきましては、定額減税が終了したことにより6,578万円の減となっております。
地方交付税につきましては、令和6年人事院勧告による公務員の給与改定等に要する費用など、地方財政計画において地方交付税が増額となったことから、前年度と比較して8,000万円の増を見込んでおります。
国庫支出金につきましては、前年度と比較しまして3億7,239万8千円と大幅な増となっております。自治体情報システム標準化に対応するための経費や児童手当の拡充、障がい者自立支援給付費負担金の増に加え、石川こども園の大規模改修工事補助などにより増となっております。
また、府支出金につきましては主に、障がい者自立支援給付費負担金や小中学校のG1GAスクール構想によるタブレット端末の更新、農村地域防災減災事業補助金などにより、9,123万4千円の増となっております。
町債でありますが、総額で2億2,460万円の借入れを予定しており、前年度と比較いたしまして、9,160万円の増となっております。
主なものといたしましては、町中心地区再編整備に伴います町有3施設の解体撤去や小中学校のG1GAスクール構想によるタブレット端末の更新などがありますが、一方で、臨時財政対策債は、平成13年度の制度創設以来、初めて新規発行額がゼロとなりました。
次に、基金繰入金ですが、出生時に5万円を給付する育児・子育て応援事業、1歳児及び2歳児に各5万円を給付する育児・子ども手当給付事業、就学前児童の副食費に加え主食費への助成事業、学校給食費無償化事業など教育・子育て基金から8,198万9千円の取り崩しを予定しております。
また、町中心地区再編整備に伴う交通連結拠点整備などに、公共公益施設整備基金から2,464万8千円の取り崩し、このほか、ふるさと応援基金や自然と歴史のふるさとづくり基金の取り崩しを予定しております。
さらに、令和7年度は、町債の償還のため減債基金を1億円取り崩す予定をしており、非常に厳しい財政状況となっております。
なお、これに加え、一般会計予算の収支財源不足額につきましては、財政調整基金のとりくずし5億4,366万8千円により対応しておりますが、今後の行財政運営を見極めつつ、その執行につきましては慎重に対応してまいります。
続きまして、歳出でございます。
新規施策及び重点的に取り組む施策を中心に、まちづくり計画における6つの政策毎に、その概要を述べさせていただきます。
政策No1 安全・安心にすめるまち
近年では台風や線状降水帯による大雨など土砂災害が激甚化しており、災害の発生状況に応じて迅速に対応できるよう、本町におきましても気象台等とのホットラインの設置や土砂災害タイムラインを活用した災害対応に取り組んでいます。
また、災害時に1人で避難することが困難な要支援者の対応について、関係部局とネットワークを構築し情報共有などを行う体制を整えていきたいと考えております。
昨年は、初めて南海トラフ臨時情報が発令されるなど災害への備えが求められており、能登半島地震の教訓から国の補正予算を受けて、令和6年度補正予算で対応し、防災備蓄品を令和7年度に充実してまいります。
防災・減災等の観点から、大規模災害が発生しても致命的な被害を負わない強靭な地域をつくるため、国土強靭化計画の次期計画の策定に取り組みます。
また、災害の未然防止や安全性の確保のため、さくら坂梅川調整池の浚渫工事、下河内地区の急傾斜地崩壊防止工事負担を行うとともに、水防ため池の西新池の改廃の設計や代替水源の調査を行います。さらに、土砂災害特別警戒区域内の住宅の移転・補強や除却費の一部補助も引き続き実施いたします。
消防・救急体制については、5市2町1村で構成する大阪南消防組合が令和6年4月から運用が開始され、統合前の各消防本部管轄の隣接地においては、現場到着時間の短縮にもつながっており、広域化の効果が表れています。また、令和6年度に予算計上されました河南出張所への消防車の配備ですが、車体の納品の遅れなどから令和7年度に繰り越し、令和7年9月に配備する予定となっております。
地域の防災力の強化として、地域の安全を守る消防団の団員確保に努め、自主防災組織の活動について、引き続き支援してまいります。
また、大規模災害時など地区における消火活動や初期消火が実施できるよう可搬式小型ポンプの貸与や、令和8年9月に開催予定の第70回大阪府消防操法訓練大会(小型ポンプ操法の部)に、南河内地区代表として河南町消防団が出場するための可搬小型ポンプを購入します。
近年では線状降水帯による大雨など土砂災害が激甚化しており、土砂災害タイムラインを活用するとともに、地域版ハザードマップをもとにコミュニティタイムラインの作成支援に取り組み、町と地域が危険箇所の情報を共有しタイムライン防災を推進します。
災害時には、自助・共助・公助の取り組みが重要となります。住民の防災士資格取得の促進、ファイアジュニアやファイアチャイルドの育成、例年実施している関係機関が一同に会する町防災訓練に加え、地域で実施されます避難訓練等への活動助成を実施します。
防犯力の強化として、他市町村との境界や地区間などに防犯カメラの更新、地域が設置する防犯灯や防犯カメラ、その電気料金の一部補助を実施するとともに、安全・安心メールの配信など引き続き実施します。
また、こどもを犯罪から守るため、地域における青色回転灯防犯パトロールや見守り活動など、地域ぐるみの防犯対策への支援や小学校1年生に防犯ブザーの配布を引き続き行ってまいります。
消費者保護の推進にあっては、巧妙化する特殊詐欺が増加しております。多種・多様化する悪徳商法や消費者問題について、ホームページや広報紙を通じて、引き続き啓発をしてまいります。
また、消費生活相談業務についても、近隣市町村と共同して引き続き、実施してまいります。
交通安全対策としまして、令和5年から着用が努力義務化されました自転車用ヘルメットの購入助成を実施しますが、令和8年6月をもって終了する予定としております。
また、道路区画線やカーブミラー、ガードレール等の交通安全施設の整備により、交通の円滑化や交通事故の防止に努めるとともに、警察などの関係機関と連携した交通安全運動や啓発活動を通じて、住民の交通安全意識の向上に取り組みます。
No2 子育てと教育のまち
安心して子どもを生み育てられる環境を実現するため、母子が健康を保持できる各種健診や医療体制の整備など取り組んでまいります。
全ての妊産婦等に寄り添い、妊娠期から出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行うとともに、必要な支援につなぐ伴走型相談支援の推進を図ります。
これまでの妊産婦健診や乳幼児健診に加え、新たに「1か月児」及び「5歳児」健診を実施し、出産後から就学前まで切れ目のない支援を行うとともに、産前・産後サポート、産後ケアなどに引き続き取り組みます。
また、国の制度による妊娠及び出生したこどもに各5万円を給付する経済的支援を行っています。町独自施策としては、出生児に5万円、1歳児に5万円の給付を引き続き実施します。令和7年度からは2歳児まで対象を拡充し、合計で15万円の給付を実施してまいります。
保健師や助産師、管理栄養士等による教室の開催や家庭訪問を通じて、育児に関する正しい知識の普及や孤立防止にも取り組みます。
さらに、近隣市町村などと連携して小児救急医療体制の維持に取り組むとともに、子どもに対する各種予防接種を引き続き行ってまいります。
従前より、児童及び妊産婦の福祉や母子保健の相談等は子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)と子育て世代包括支援センター(母子保健)において実施しておりましたが、この2つを統合し全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に相談支援を行う機能を有する「こども家庭センター」を令和7年度に設置いたします。
核家族化の進行や地域のつながりが希薄化する中で、子育ての悩みについて相談に応じる臨床心理士による心理相談員の配置、子育てセンター(おやこ園)で提供する親子同士の交流の場や子育てに関する情報収集、家庭保育が困難な場合などに利用できる一時預かりサービス(ぽけっとルーム)などを引き続き実施してまいります。
また、中村こども園で「こども誰でも通園制度」を試行的に実施し、月一定時間までの利用可能枠の中で就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できるサービスを実施します。
障がいを抱える子どもや虐待を受けている子どもを早期に把握し、関係機関によるネットワークや学校のスクールソーシャルワーカーなどによって、早期発見・早期支援に取り組んでまいります。
保護者の経済的負担の軽減等を目的に、第2子以降保育料無償化を引き続き実施するとともに、令和7年度からは中村こども園の給食費の完全無償化を実施します。その他の幼児教育・保育施設については、副食費の助成に加え、主食費についても助成を行います。
令和4年度から実施している学校給食費の全額助成事業は、学校給食会計から町一般会計にて執行する公会計化への移行に伴い、給食費の完全無償化を実施するとともに、私立等の小中学校へ通学する児童・生徒等の給食費助成を開始し町在住の児童・生徒全員を対象に給食費の助成を実施します。
学校給食センターでは、町内産の食材を使用した給食の提供等により食育を進めるとともに、児童生徒から募集した献立の実施、郷土料理や旬の食材を取り入れた行事食の提供など、魅力ある学校給食に引き続き取り組んでまいります。
公私連携幼保連携型認定こども園として運営している石川こども園ですが、社会福祉法人千早赤阪福祉会との協定により、これまでの運営実績を踏まえ、引き続き安定した教育・保育ができるよう連携してまいります。
また、石川こども園の大規模改修工事が令和7年度から令和8年度にかけて実施されることから、国・町から事業費の4分の3相当の補助を行い、保育環境の整備を図ってまいります。
中村こども園の職員配置につきましては、国の基準に合わせ4・5歳児については、30対1から25対1へ、3歳児については、20対1から15対1となるよう職員配置の対応を行います。なお、石川こども園については、令和6年度に引き続き、国の基準に合わせた職員配置が行われます。
子どもの医療費については、医療費の一部を助成することにより、子育て世帯の負担軽減や若者の健全な育成などに寄与すべく、22歳以下の住民に対する医療費助成制度(U―22含む)を引き続き実施します。
地域ぐるみの子育てにあっては、放課後や土曜日に親子が参加できる教室の開催や、乳幼児の読書活動を推進するブックスタート事業を引き続き実施し、親子が触れ合える機会を提供してまいります。
また、教員の負担軽減を図り、いじめ防止・不登校児童生徒の支援・学力向上の取り組み等に、より一層注力できる環境を整備するため、印刷業務や簡単な採点事務等を担う教員業務支援員の配置、中学校へのAIによる採点補助システムの導入、部活動支援員の配置等、教員の働き方改革を進めます。
さらに、「地域学校支援コーディネーター」を配置し、学校が、地域や各種団体等とより一層連携し、子どもたちの育ちや学びに係る様々な課題の解決を図るため、コミュニティスクール構想を推進してまいります。
何らかの理由で学校へ行けない、または行きづらい児童・生徒への支援・指導につきましては、教育支援センターを設置し対応するとともに、学校内の居場所として設置された校内特別支援ルームへの指導員派遣を行っております。令和7年度には、小学校だけでなく、新たに中学校にも指導員を派遣し、個に応じた適切な支援・指導を強化してまいります。
また、いじめ問題への対応や不登校児童生徒の支援等については、弁護士やスクールカウンセラー等の専門家を交えた河南町立等学校園支援チームによる取り組みを支援してまいります。
さらに、学校にこども支援スタッフを配置するなど、支援が必要な児童生徒が学校生活を安心して送ることができる環境の整備に引き続き取り組みます。
令和2年度からGIGAスクール構想による授業や家庭学習で活用できるデジタル教材を用いて、効果的な授業づくり等に取り組んでおりますが、タブレット端末のバッテリーの劣化や故障が多くなっているため、令和7年度にタブレット端末の更新を実施します。
また、教育環境の改善と脱炭素化への取り組みのため、中学校校舎と近つ飛鳥小学校校舎及び体育館等の照明器具をLED化する実施設計を行います。
さらに、子どもたちが安全に活動できる環境を整え、自然災害の増加に伴う避難所の環境改善を行うため、国の補正予算を受けて、令和6年度補正予算で対応し、令和7年度に小学校体育館の空調設備を整備します。
生きた英語に触れる機会を持てるよう、引き続き小・中学校に外国語指導助手(ALT)を配置し、中学生の英語検定受験を実施するとともに、学校図書館司書を配置し、読書への関心を高めるなど、さらなる学習意欲の向上に取り組んでまいります。
令和7年度は、2025年大阪・関西万博が開催されます。次代を担う子どもたちに最先端の技術やサービス等に直接触れる体験により将来に向けて夢と希望を感じ取ってもらうため、大阪府の無料招待事業が実施され、本町の各小中学校では、学校行事として参加し、現下の交通事情を踏まえスクールバスで対応する予定です。
また、本町でも4歳から17歳の児童生徒及び18歳以上の高校生を対象とした無料招待を実施します。
No3 みんなが生涯活躍できるまち
住み慣れた地域の中で、すべての住民が生き生きと暮らしていくためには、行政、住民が協働して地域の総合的な福祉の推進に取り組んでいく必要があります。
一体的に策定した第4期地域福祉計画と地域福祉活動計画に基づき、社会福祉協議会や民生委員児童委員協議会など各種団体と連携して、地域ニーズにあったサービスの充実に努めてまいります。
社会福祉協議会には、各種支援施策のコーディネーター的役割を担うコミュニテイソーシャルワーカーの配置、地域資源の開発やネットワークの構築など地域支え合い推進員の配置を引き続き実施します。
また、これまでの福祉制度・政策の狭間や複合的な支援ニーズに対応するため重層的支援体制の拡充を図り、日常生活において、支援が必要となった人が、できる限り自立して快適な生活を送れるよう適切なサービス給付に努めます。
次に、高齢者福祉につきましては、第9期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に基づき可能な限り健康で自立した生活が送ることができるよう、地域の実情に応じた高齢者福祉、介護保険の支援体制を計画的に確保することに努めます。
認知症への対応として認知症地域支援推進員の配置や認知症初期集中支援チームの設置など本人及び家族への支援、認知機能の把握・改善のためのソフトを活用した認知機能チェックや認知症予防教室の実施、認知症カフェの支援に取り組むとともに、徘徊高齢者の安心対策としてSOS登録を引き続き行います。
要介護・要支援にならないために心身の状態を維持(向上)する取り組みである介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)において、運動機能の維持・向上を図る通所型サービスC事業や訪問型サービスDによる町外への移動支援を実施します。
健康寿命の延伸への取り組みとして、これまで行ってきた健康診査や健康教室、予防接種などを通じた疾病の予防や早期発見に努めるとともに、65歳以上の高齢者を対象に5歳刻みにより、帯状疱疹ワクチンの定期接種を新たに実施します。
後期高齢者の保健事業につきましては、歯、噛む力や飲み込む力など口まわりの健康維持・改善を目的としたオーラルフレイルに関する保健事業を新たに実施します。
また、かなん健康マイレージ事業、100歳体操の普及啓発、介護予防に関する啓発や介護予防プログラムの充実に引き続き取り組みます。
さらに、がん治療にともなう医療用ウィッグ又は乳房補整具購入費の一部助成を引き続き実施します。
国民健康保険については、令和6年度から大阪府内統一保険料となっていますので、大阪府の試算に基づき保険料が決定いたしますが、令和7年度は保険給付費が減となる見通しで、大阪府国保特会の余剰金の活用や統一達成による国からの交付金などを受けて、昨年度より保険料率が下がることとなりました。賦課限度額につきましては、後期高齢者分で2万円の引き上げとなり、全体で106万円となっております。
国保の保健事業におきましては40代・50代の特定健康診査の受診率低下を解決するため、30代からの健診や保健指導を引き続き行います。若年層の健康への関心を高め、生活習慣病を予防することで、医療費の抑制や健康寿命の延伸を図ってまいります。
後期高齢者医療制度においては大阪府広域連合が2年に一度保険料を改定しており、令和7年度は令和6年度と同額となっております。しかしながら昨今の経済動向等を踏まえ、保険料の5割軽減及び2割軽減の対象者を拡大する見直しが行われております。
障がいのある人が、その意思決定に基づいて、その人らしく生活ができ、障がいのある人とない人が、互いに理解しあい支えあってきずなを深め、共にいきるまちを目指し、第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画により、また、健やかに心豊かに自分らしく安心して生きることができるまちを目指し、一体的に策定した健康かなん21(第3次)・第4次河南町食育推進計画・第2次河南町いのち支える自殺対策計画に基づき各種施策に取り組んでまいります。
生涯学習の場として、公民館や図書館を多くの方々に利用いただけるよう、各種講座の開催やさらなる蔵書の充実に努め、住民の生涯学習の取組を進めます。
令和元年度以降、中学生の海外への派遣を見合わせていましたが、令和7年度は、中学生異文化体験事業として、中学2年生・3年生を対象に、オーストラリアでの体験学習を実施いたします。また、小学5年生・6年生・中学1年生を対象にイングリッシュキャンプを実施するなど、より英語や異文化への興味・関心を高める機会づくりに努めてまいります。
テニスコート改修事業としまして、町立テニスコートの人工芝全面張替え工事を実施します。改修完了後は、リニューアル記念大会を開催する予定です。さらに、体育施設の環境整備及び脱炭素への取り組みとして、町立総合体育館・野球場・テニスコートの照明のLED化を実施します。
スポーツの推進にあっては、ヨガ教室やかけっこ教室、こども水泳教室などを開催し、町スポーツ推進委員などと連携してさらなるスポーツ振興を図ってまいります。
基本的人権が尊重された差別のない明るいまちの実現を目指して、「河南町人権をまもる会」などと連携し、人権を考える町民の集いや啓発冊子の作成などの人権啓発に努めるとともに、人権に関する相談を行ってまいります。
また、住民一人ひとりが、性別にかかわりなく、互いの人権を尊重し、個性と能力を発揮して、多様な生き方を選択できる社会の実現を目指すため、「かなんジェンダー平等推進プラン~第3期~」により各種施策に取り組み、各種講座や講演会、男女共同参画ニュースなどを通じた啓発活動、相談事業を実施してまいります。
No4 快適で賑わいのあるまち
地域のコミュニティを維持し、活力あるまちであり続けるためには、子育て支援に加え、移住定住を促進することにより、本町の人口減少を抑制していく取組が必要です。
町では、Uターンや定住を図るため、親子での同居・近居を目的として住宅を取得またはリフォームする子世帯等を対象にした三世代同居・近居支援に引き続き、取り組んでまいります。
また、空き家バンクへの登録をさらに促すことを目的として、町の空き家バンクに登録された空き家が成約となった場合に成約奨励金を引き続き支給してまいります。
農業の生産性の向上や効率化、農地の利用集積等による農業経営の安定化を図るため、府営事業として北加納・南加納・寺田地区における「ほ場整備事業」を進めています。今後、整備事業が本格化することから、地元農家と大阪府とともに事業の推進を図ってまいります。また、河南西部土地改良区内の農業用貯水施設の改修に対する支援や中地区内の水路改修など生産基盤の整備を図ってまいります。
有害鳥獣による農作物被害の防止対策として、資材等の購入に対する補助金の交付を引き続き実施してまいります。
また、新たな担い手の育成、農業経営の安定化を図るため、農業次世代人材投資事業を引き続き実施するとともに、大阪版認定農業者等による機械・施設整備補助を実施し、農業振興施策の充実に努めてまいります。
林業については、森林の保全や林業の振興に取り組んでいくため、森林環境譲与税を活用し、森林整備や間伐材の搬出経費の一部補助を行うとともに、おおさか河内材を活用した出生記念木製玩具の配布や庁舎1階ロビーにパンフレット用ラックの整備を実施します。
産業振興を図るためには、経営改善支援を含めた産業の育成や、新たな企業の誘致等に取り組んでいく必要があります。
町内で新たに創業する者に対し、経費の一部を補助する取組を進めてまいります。
町中心地区の再編整備については、令和5年に策定しました基本構想に基づき、令和7年度は町有3施設(旧わかば作業所、旧青少年スポーツセンター、旧中央保育園分室)の解体撤去工事、旧町民体育館の解体撤去の実施設計を行うとともに、交通連結拠点の交通広場及び府道交差点の詳細設計を実施します。
地域経済活性化として、町内の加盟店で利用できる電子地域通貨カナちゃんコインの決済額に応じたポイント付与を引き続き実施してまいります。
また、産業振興のため、本町のふるさと納税制度について、積極的なPRや新規返礼品の開拓に取り組み、ふるさと納税の獲得に努めます。
さらに、企業版ふるさと納税にも取り組み財源確保に努めてまいります。
道の駅かなんの拡張エリアについては、引き続き民間企業から人材を受け入れ企画立案など検討してまいります。
インフラの整備にあっては、交通利便性の向上や地域産業発展のため、引き続き、主要地方道柏原駒ヶ谷千早赤阪線(山城バイパス)、国道309号(河南赤阪バイパス)などの幹線道路の早期整備を要請するとともに、国の新広域道路交通計画に調査中路線として位置付けられた大阪南部高速道路(大南高)の実現を、関係機関と連携して働きかけます。
特に、主要地方道柏原駒ヶ谷千早赤阪線(山城バイパス)については、大阪府及び太子町と連携を図り、事業促進について、その役割を果たしてまいります。
また、集落内道路や集落間道路の舗装打ち替え工事、橋梁長寿命化計画による修繕工事を実施するなど、引き続きインフラの適正な維持管理に取り組みます。
公園の整備については、良好な環境を維持するとともに、老朽化した遊具の更新などを引き続き実施します。
下水道整備にあっては、ストックマネジメント計画によりさくら坂地区のマンホール蓋の取り替え工事を実施します。また、令和6年度で実施しました不明水調査の結果に基づき、雨天時侵入水対策計画を策定するとともに、流域関連公共下水道に係る基本計画の改定を実施します。
上水道につきましては、令和3年度から大阪広域水道企業団に統合し運営しておりますが、河南水道センターは本年4月から本町と太子町、千早赤阪村のセンターを統合し、太子町の板屋橋浄水場で南河内地域水道センターとして上水道事業を行うこととなっております。
地域の活性化をより一層進めていくため、民間企業等と連携して町の産業振興や観光振興を図っていくとともに、大阪芸術大学や近つ飛鳥博物館の協力を得て、各種講座やぷくぷくサンデーコンサートを実施し、住民の皆さんの生涯学習に対する幅広いニーズに対応できるよう、文化・芸術の振興に引き続き取り組んでまいります。
地域公共交通では、河南町地域公共交通計画及び4市町村地域公共交通計画により、本町では、現行の金剛ふるさとバス・カナちゃんバス・やまなみタクシーを一体で維持することとし、今後は、地域特性に応じた最適な公共交通サービスを協働・連携のもとに検討してまいります。引き続き住民の移動手段を確保し、地域の公共交通としての役割を担ってまいります。また、大阪府で進められております新モビリティへの取り組みにつきましては、連携を密にして取り組んでまいります。
令和7年度は、2025年大阪・関西万博が開催されます。本町も大阪ウイーク「大阪の祭~EXPO2025~春の陣」に2地区のだんじりが出展することとなりその一部を助成するとともに、南河内LIVE・ART・EXPOには大阪芸術大学と協力し出展する予定であります。この万博を通じ、本町の魅力を積極的にPRしてまいります。
No5 自然と歴史に囲まれたまち
都市近郊に位置しながら、多くの緑に囲まれた豊かな自然と歴史を感じる環境や文化的な景観を観光資源として活用し、交流人口を増加させることが大切です。
かなん桜プロジェクトは、桜の植樹をはじめ、町の桜の魅力を町内外に発信するとともに、かなん桜まつりを開催します。
本町には、全国的にも珍しい双円墳である金山古墳(国史跡指定)や、日本遺産に認定された「葛城修験」に属する2つの経塚など、非常に長い歴史を有した文化財があります。なかでも町のシンボル的存在である金山古墳については、土砂流入などが激しい石室内部や石棺などの修復及び保護、周辺地の保全活用方法について、史跡金山古墳等保存活用審議会を立ち上げ、検討を行ってまいります。
葛城修験につきましては、3府県20市町村で構成する葛城修験日本遺産活用推進協議会と連携して、魅力発信に努めてまいります。
また、本町では「美しい河南町基本条例」を策定し、「美しい山々がそびえ、美しい川が流れ、美しい心が集うまち」の実現に取り組んでいます。
町全体で行うクリーンキャンペーンなどを通して、景観の保全・美化にも取り組んでまいります。
生活様式の多様化により、本町から排出されるゴミの排出量は増加傾向にありますが、引き続き、ごみの減量化及び再資源化について、住民の皆さんと共に進めてまいります。なお、南河内環境事業組合で令和4年度から進められておりました第1清掃工場の整備が令和6年度に完了したことによりゴミ処理の体制が整いました。
本町では、ゼロカーボンシティを宣言しており、その取り組みとして、引き続き、太陽光発電システムの設置補助や電気自動車等充電設備の設置補助を行うとともに体育施設の照明のLED化など、二酸化炭素排出実質ゼロに向けた取り組みを行ってまいります。
No6 一歩先を行くまち
現在、社会のデジタル化が大きく加速しております。その要因としては、新型コロナウイルス感染症拡大などが挙げられると思います。
ますます住民のニーズが多様化するなか、デジタルトランスフォーメーション(DX)を活用した行政運営を推進していくことが重要となります。
まず、国が進める自治体情報システム標準化(ガバメントクラウド)により基幹業務の効率的な管理運営に取り組み、一部の業務について令和7年度から移行します。
また、限られた人員のなか、業務の効率化と職員の働き方改革を図るため、地方創生人材支援制度による専門家を活用し、RPAなどのDXの取組を推進します。
本町では、スマート窓口の環境整備に取り組んでおります。「書かない窓口」は、来庁者は申請に必要な事項を記載する必要がなくなります。「ワンストップ窓口」は、転入転出など住民異動に伴う定型的な手続きは1か所で完了するようになります。また、番号発券機のほかセミセルフレジを導入したことにより、手数料の納付などがキャッシュレスでの対応が可能となります。窓口業務の迅速化と住民の皆様の負担軽減に努めてまいります。
さらに、公開型GISにより、地図と紐づく分かりやすい情報として誰もが入手できる情報提供サービスの実施や、マイナンバーカードを活用したオンライン申請の拡充などにも取り組んでまいります。
地方税については、これまでも地方税の納付手続きの電子化に取り組んできましたが、今後、電子申告手続きの拡大として、個人住民税申告の電子化、二輪車等の申告・申請の電子化に取り組んでまいります。
最後に、令和3年に策定しました「河南町まちづくり計画」は、計画期間が令和7年度までとなっております。国においては地方創生2.0の「基本的な考え方」が示されており、本町でも、かなんまちづくり基本条例にもとづくまちづくり計画とまち・ひと・しごと創生法にもとづく総合戦略の一体的な次期計画の策定に取り組んでまいります。
おわりに
今会議におきましては、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてのほか、11件の条例の制定及び改正の議案、また、教育委員の任命にかかる議案を上程させていただいております。
以上、令和7年度当初予算に関連いたしまして、主要な施策の一旦をご説明いたしましたが、今議会に提案させていただきました諸案件につき、ご審議のうえ、原案どおりご可決・ご同意賜りますようお願い申し上げます。
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 まちづくり秘書課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:210・211・213・215)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール/秘書企画係:hisho@town.kanan.osaka.jp
Eメール/広報担当:kouhou@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム






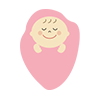

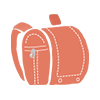

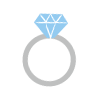

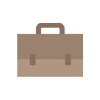

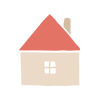



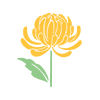

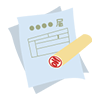





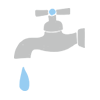
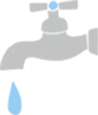
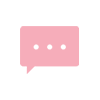


















更新日:2025年03月05日