児童手当制度改正(拡充)のお知らせ
児童手当の抜本的拡充について(令和6年10月分から)
令和5年12月22日に閣議決定された「こども未来戦略」で掲げる「こども・子育て支援加速化プラン」に基づき、児童手当の抜本的拡充が実施されることとなりました。これにより、令和6年10月分からの児童手当が以下のとおり変わります。
拡充後(令和6年10月分以降)の手当の初回支給月は、令和6年12月です。
児童手当の抜本的拡充による変更点
変更点
|
主な変更 |
改正(拡充)前 (令和6年9月分まで) |
改正(拡充)後 (令和6年10月分から) |
|---|---|---|
|
支給対象 |
中学校修了前までの児童(15歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方 |
高校生年代までの児童(18歳到達後の最初の年度末まで)を養育している方 |
|
所得制限 |
所得制限あり |
所得制限なし |
|
手当月額 |
●3歳未満 一律:15,000円 ●3歳~小学校修了まで 第1子・第2子:10,000円 第 3 子 以 降 :15,000円 ●中 学 生 一律:10,000円 ●所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 一律:5,000円(特例給付) ●所得上限限度額以上:支給なし |
●3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第 3 子 以 降 :30,000円 ●3歳~高校生年代 第1子・第2子:10,000円 第 3 子 以 降:30,000円 |
|
支給月 |
年3回(各前月までの4ヶ月分を支払) 10月分~1月分…2月 2月分~5月分…6月 6月分~9月分…10月 |
年6回(各前月までの2ヶ月を支払) 10・11月分…12月 12・1月分…2月 2・3月分…4月 4・5月分…6月 6・7月分…8月 8・9月分…10月 ※支給月の5日(銀行休業日の場合はその後の営業日)に振り込みます。 |
|
多子加算の算定対象(カウント方法) |
18歳到達後の最初の年度末までの児童 |
18歳到達後の最初の年度末までの児童 + 児童手当受給者に経済的な負担等がある18歳年度末以降から22歳年度末までの子 |
今回の改正により手続きが必要な方
|
手続きが必要な方 |
手続方法・提出書類 |
|---|---|
|
(1)中学生以下の児童を養育しておらず、 高校生年代の児童を養育している方 (2)所得上限限度額超過で児童手当(特 例給付)の支給対象外である方 |
●児童手当認定請求書 【必要な添付書類】 ・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、通知カードなど) ・請求者名義の通帳又はキャッシュカード ・請求者の健康保険証の写し
|
|
(3)新たに多子加算の算定対象となる18歳年度 末以降22歳年度末までの子と高校生年代まで の児童の合計人数が3人以上の方 ★新たに児童手当の対象となる方だけでなく、 現在、受給中で該当する方も提出が必要です。 |
●児童手当額改定認定請求書 ●監護相当・生計費の負担についての確認書 |
|
(4)支給対象となる高校生年代の児童の住所が 河南町にない方 |
●別居監護申立書 【必要な添付書類】 ・児童の属する世帯全員の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載があるもの) |
添付書類を確認し、手続きをお願いします。
手続き確認フローチャートは次のとおりです。
申請様式
1.新規認定請求が必要な方
※上記表の(1)・(2)にあてはまる方
全員提出頂く必要があるもの
児童手当認定請求書(記入例)(PDFファイル:412.2KB)
該当する方のみ必要なもの
・請求者と支給対象児童(18歳到達後最初の年度末までの児童)が別居している場合
(注)児童の個人番号(マイナンバー)を必ず記入し、児童の属する世帯全員の住民票の写し(個人番号の記載があるもの)を添付書類として提出してください。
・18歳到達後最初の年度末から22歳到達後最初の年度末までの子がいて、その子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合であって、その子を含めて3人以上を養育している場合
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:89.5KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:307.5KB)
(注)子の個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください
その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。
2.額改定請求が必要な方
※上記表の(3)にあてはまる方
★現在児童手当等を受給しており、児童との別居等により支給要件児童(第3子以降増額のための児童数のカウント対象となっている児童)として認定されていない18歳到達後最初の年度末までの児童と中学生以下の児童を監護・養育している場合
(注)支給要件児童(第3子以降増額のための児童数のカウント対象となっている児童)として認定されており、現在児童手当等を受給している方は手続不要です。
但し、現在児童手当を受給しており、18歳到達後最初の年度末から22歳到達後最初の年度末までの子がいてかつ、その子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合であって、その子を含めて3人以上を養育している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
全員提出頂く必要があるもの
児童手当額改定請求書(記入例)(PDFファイル:365.6KB)
該当する方のみ必要なもの
・請求者と支給対象児童(18歳到達後最初の年度末までの児童)が別居している場合
(注)児童の個人番号(マイナンバー)を必ず記入し、児童の属する世帯全員の住民票の写し(個人番号の記載があるもの)を添付書類として提出してください。
・18歳到達後最初の年度末から22歳到達後最初の年度末までの子がいて、その子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合であって、その子を含めて3人以上を養育している場合
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:89.5KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:307.5KB)
(注)子の個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください
その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。
3.確認書の提出が必要な方
※上記表の(3)にあてはまる方
★現在児童手当等を受給しており、18歳到達後最初の年度末から22歳到達後最初の年度末までの子がいてかつ、その子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合であって、その子を含めて3人以上を養育している場合
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:89.5KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:307.5KB)
(注)子の個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください
その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。
受付期間
令和6年9月24日(火曜日)から令和6年10月25日(金曜日)まで
(初回は令和6年12月振込となります)
ただし、申請猶予の経過措置により令和7年3月末までに申請していただければ、新制度が施行される令和6年10月分から遡って支給開始となります(手当の振込は遅れますのでご了承ください)。
河南町に住民票があり手続が必要と思われる方には9月中旬に通知を送付しています。
通知が届いていない方で申請が必要な方(保護者のみが町にお住まいの方など)はご連絡ください。
窓口での申請は大変混雑が予想されますので郵送による申請にご協力をお願いします。
※申請が必要な方は申請しなければ手当は支給されませんので、手続きをお忘れなくお願いします。
期限までに「児童手当認定請求書」の提出がない場合(*新規で手当が認定される方)は、令和6年10・11月分の手当の支給月は12月ではなく、令和7年2月以降になります。同様に、「児童手当額改定認定請求書」「監護相当・生計費の負担についての確認書」についても、提出がない場合は、改正(拡充)後の多子加算額の適用がない手当額が支給されます。
なお、改正(拡充)に係る手続きの最終期限は、令和7年3月31日です。
最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及して手当の支給・多子加算の適用はできません(手当の支給・多子加算の適用は、認定請求や確認書を町で受け付けした月の翌月分からとなります)。
手続きが不要で、支給額及び支給期間が変更となる方
・所得制限により、特例給付を受給している方
・高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の児童を養育している世帯で、町の保有する受給者情報に当該児童の登録がある方
・3人以上の児童を養育し、すでに多子加算により、第3子以降の児童の手当額が増額となっている方(大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)のお子さんを養育していない方)
・児童手当(特例給付)を受給している方のうち、養育している児童が2人以下で、いずれも中学校修了前の児童の場合等、制度改正により手当額に増減がない方
支給額が変更となる方には令和6年12月上旬に手当額改定(増額)の通知をお送りする予定です。
公務員の方
児童の保護者(生計中心者)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が児童手当の手続き先です。今回の改正(拡充)に伴う手続きは、町ではなく勤務先(所属庁)で行ってください。なお、手続きの時期等は、それぞれの勤務先(所属庁)へお問い合わせください。
その他
・令和6年9月30日以前に町から転出する場合は、転入先の自治体で手続きを行ってください。
・制度改正に伴い、これまで支給月に送付していた「支払通知書」は廃止となります。
児童手当の制度改正のパンフレット
この記事に関するお問い合わせ先
郵便番号585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:161・162)
ファックス番号:0721-93-7560
Eメール:kodomo@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム






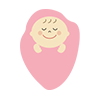

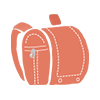

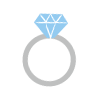

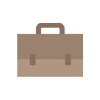

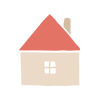



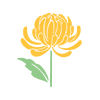

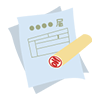





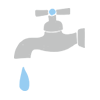
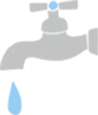
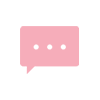


















更新日:2024年09月18日