ひとり親家庭などの皆様へのお知らせ
ひとり親家庭医療費助成
ひとり親家庭に対し、医療費の一部を助成することにより、生活の安定と児童の健全な育成を図ることを目的としています。
助成の対象
入院・通院・調剤などにかかる保険適用の医療費
訪問看護ステーションが行う訪問看護(保険適用分)
助成の対象外
- 健康保険が適用されないもの(健康診断、薬の容器代、差額ベッド代など)
- 交通事故など、加害者(第三者)から傷害を受けて医療機関を受診した場合
対象者
河南町に居住し、前年中の所得が所得制限内(児童扶養手当に準ずる)で、次のいずれかに該当する者。
- ひとり親家庭の18歳(の誕生日以降最初の3月31日)までの児童
- 1.の児童を監護する父または母
- 1.の児童を養育する養育者
※裁判所から配偶者暴力など(DV)に関する保護命令が出されたDV被害者を含みます。
ただし、次のいずれかに該当する者は除きます。
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
- 児童福祉法に基づく措置により医療費の支給を受けている者及び同法第24条の2第1項に規定する指定知的障害児施設等に入所又は入院している者(通所している者を除く。)
ひとり親家庭に該当される方
次のいずれかに該当する児童の父または母がその児童を監護する家庭をいいます。
- 父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係にあった場合を含む)
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からの保護命令(その児童の母または父の申立てにより発せられたものに限る)を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
養育者とは
次のいずれかの児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する者をいいます。
- 父母が死亡した児童
- 父または母が監護しないひとり親家庭の児童
助成内容
医療機関で「ひとり親家庭医療 医療証」とマイナ保険証などを提示してください。
※「ひとり親家庭医療 医療証」は、大阪府外では使用できません。府外で受診した場合は、保険診察医療費を一旦窓口で負担していただき、後日払い戻しの手続きが必要になります。
| 種類 | 自己負担金額 | 内容・補足 |
|---|---|---|
| 外来受診 (歯科も含む) |
医療機関ごと ※同月3回目以降は0円(全額助成) |
|
| 入院 |
1日 500円 ※同月3回目以降は0円(全額助成) |
|
| 調剤薬局 | 0円 (全額助成) |
|
| 治療用装具 | 0円 (保険適用の範囲内で全額助成) |
|
- 同じ医療機関でも、「入院」と「通院」の日数は別カウントになります。
また、同じ医療機関で「歯科」と「それ以外の診療科」にかかった場合も、同様です。 - 1か月の間に複数の医療機関を受診し、支払った自己負担金が2,500円を超えた場合、払い戻しの手続きにより、超過分の金額を助成します。(ただし、一部自己負担額は個人単位で計算し、世帯の合算は行いません。)
払い戻しの手続き
大阪府外で医療機関を受診した場合などは、以下のものを役場こども1ばん課までお持ちください。医療機関で負担した金額とひとり親家庭医療自己負担額の差額を口座振替にて助成します。
なお、健康保険組合等から高額療養費が支給される場合は、それらを受給してから申請してください。
手続きに必要なもの
- 医療機関発行の領収書
- 振り込み先のわかるもの
- ひとり親家庭医療 医療証、資格確認書など
- 健康保険組合などが発行した支給決定書(コピー可)
※治療用装具など高額療養費に該当する場合、必要です。 - 医師が発行した証明書(コピー可)
※治療用装具などの場合、必要です。
振り込みについて
- 毎月末日に受け付けを締め切り、翌月末までに振り込みます。
- 医療費給付の決定通知書を送ります。
- 審査などの確認作業のため、振り込みが遅れる場合があります。あらかじめ、ご了承ください。
その他、注意事項
- 医療機関発行の領収書は、必ず原本を提示してください。助成申請済みであることを示すスタンプを押印のうえ、領収書はお返しします。
- 払い戻しの有効期間は、5年間です。治療用装具などの場合は、2年間となることがあるので役場こども1ばん課にご相談ください。
ただし、診療当時に助成の対象でない場合、払い戻しはできません。
児童扶養手当の支給
父母の離婚などによって、父または母と生計を同じくしていない児童を育成する、ひとり親家庭の父または母などに支給される手当です。
この手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
支給対象者
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(一定の障がいがある場合は20歳未満)を監護している母または児童を監護し、かつ生計を同じくする父、あるいは父母に代わってその児童を養育している養育者の方が手当を受給できます。
- 父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係にあった場合を含む)
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める一定の障がいの状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からの保護命令(その児童の母または父の申立てにより発せられたものに限る)を受けた児童
- 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。
- 受給資格者である父母、養育者または対象児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 受給資格者でない父または母と児童が生計を同じくしているとき(ただし、その父または母が政令で定める程度の障がいの状態であるときを除く)
- 父または母の配偶者に養育されているとき(配偶者には、住民票上や実態上の同居など、婚姻の届け出をしていないが社会通念上客観的に婚姻関係と同様の事情にある者も含む)
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)及び、障がい者福祉施設に入所しているとき
児童扶養手当の額
手当の額は、請求者または配偶者及び扶養義務者(請求者の父母兄弟姉妹などで、同居している方)の前年の所得によって決定されます。
令和6年11月分(令和7年1月10日支給)から第3子以降の加算額が引き上げられます。
| 令和6年4月分から10月分まで | 令和6年11月分から | |
|---|---|---|
| 1人目 |
全部支給 45,500円 一部支給 45,490円~10,740円 |
全部支給 45,500円 一部支給 45,490円~10,740円 |
| 2人目 |
全部支給 10,750円を加算 一部支給 10,740円~5,380円を加算 |
全部支給 10,750円を加算 一部支給 10,740円~5,380円を加算 |
| 3人目以降 |
全部支給 6,450円を加算 一部支給 6,440円~3,230円を加算 ※1人の児童に対し、上記の手当額が加算されます。 |
全部支給 10,750円を加算 一部支給 10,740円~5,380円を加算 ※1人の児童に対し、上記の手当額が加算されます。 |
※手当の額は「物価スライド制」の適用により変動することがあります。
児童扶養手当の支給期日
手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
| 支給日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 5月11日 | 3月分~4月分 |
| 7月11日 | 5月分~6月分 |
| 9月11日 | 7月分~8月分 |
| 11月10日 | 9月分~10月分 |
| 1月11日 | 11月分~12月分 |
| 3月11日 | 1月分~2月分 |
※支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日に支給されます。
※支給を通知する書類の送付はありませんのでご注意ください。
所得による支給制限(令和6年11月分以降)
請求者または配偶者及び扶養義務者(請求者の父母兄弟姉妹などで、同居している方)の前年(1月から9月に申請する方は前々年)の所得が、下記の限度額以上である場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給されません。
| 扶養親族等の数 | 請求者(父母または養育者) 全部を受給できる方 |
請求者(父母または養育者) 一部を受給できる方 |
配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
| 1人 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 | 2,740,000円未満 |
| 2人 |
1,450,000円未満 |
2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
| 3人 | 1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
| 4人以上 | 以下1人増すごとに 380,000円加算 | 以下1人増すごとに 380,000円加算 | 以下1人増すごとに 380,000円加算 |
| 所得制限 加算額 |
|
|
老人扶養親族1人につき6万円 ※扶養親族全員が老人扶養親族の場合は、1人を除く。 |
諸控除
緒控除の詳細
| ※寡婦控除 | 270,000円 |
|---|---|
| ※ひとり親控除 | 350,000円 |
| 障害者控除 | 270,000円 |
| 特別障害者控除 | 400,000円 |
| 勤労学生控除 | 270,000円 |
| 配偶者特別控除・雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除額 |
※受給者が父または母である場合、寡婦控除、ひとり親控除は控除されません。
養育費の加算
児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として父母または児童が受け取る金品等で、その金額の8割が、父または母の所得に加算されます。
所得の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費-8万円(社会保険料相当)-諸控除
児童扶養手当の認定請求について
必要な書類等を確認・相談のうえ、必ず請求者本人が申請をしてください。
必要となる書類等
- 請求者と対象児童の戸籍謄(戸籍抄本) 発行後1カ月以内のもの
- 請求者名義の振込先口座となる預金通帳
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
- 印鑑
- その他必要書類(要件によって必要書類が異なります)
引き続き受給するには
現況届
児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月1日~31日の間に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、前年の所得と児童の監護状況の確認及び11月以降の支給額を決定するためのものです(前年が所得制限を超えていたため手当の支給がなかった方も、資格継続のために提出が必要です)。
7月下旬に通知文等を送付しますので、期間中に必ず提出してください。
「現況届」を提出しないと8月分以降の手当が差し止めされ、2年間提出がない場合は受給権が消滅します。
支給期間等による手当の一部支給停止
手当の一部支給停止
父または母が手当を受けている場合、「支給開始月の初日から起算して5年」、または「手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年」を経過したときは、手当額の2分の1が支給停止になります。
ただし、以下の事由に該当し、期限までに必要な書類を提出した場合は、これまでどおり所得額に応じた手当が支給されます。
- 就業または求職活動等の自立を図るための活動をしている
- 政令で定める程度の身体上または精神上の障がいがある
- 負傷または疾病等により就業することが困難である
- 監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護のため就業することが困難である
要件に該当する受給資格者には、受給から5年を経過するとき及び「現況届」送付時に通知しますので、確認できる書類を添えて期限までに提出してください。
手当を受ける資格がなくなったとき
資格喪失届
- 受給資格者(父または母)が婚姻し、児童がその配偶者に養育されているとき(婚姻の届出をしていなくても、次の場合は婚姻に含まれます)
- 婚姻の届出はなくても、社会通念上、夫婦として共同生活と認められる事実関係があるとき
- 同居していなくても、頻繁に定期的な訪問があり、かつ、生活費の補助を受けているとき
- 受給資格者が児童を監護しなくなったとき
- 児童が受給資格者の元配偶者と生計を同じくするようになったとき
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)及び、障がい者福祉施設に入所したとき
- 児童が里親に委託されたとき
- 受給資格者または児童が日本に住所を有しなくなったとき
- 受給資格者または児童が死亡したとき
- その他手当を受ける資格がなくなったとき
大阪府のひとり親家庭などへの支援情報について
次のリンク先では、大阪府における 母子家庭・父子家庭・寡婦の方を支援する制度を紹介しています。
この記事に関するお問い合わせ先
郵便番号585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:161・162)
ファックス番号:0721-93-7560
Eメール:kodomo@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム






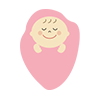

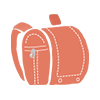

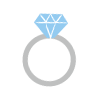

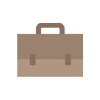

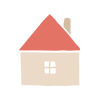



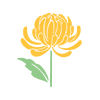

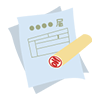





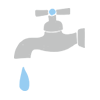
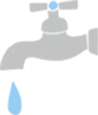
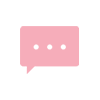


















更新日:2024年12月17日