令和6年 所信表明
はじめに
令和6年河南町議会6月定例会議の開議にあたりまして、今後の町政に関する私の所信の一旦を申し述べさせていただき、住民の皆さま並びに町議会の皆さまのご理解とご協力を賜りたく存じます。
このたび、本年3月24日執行の町長選挙におきまして、河南町長として引き続き、町政運営の舵取りを担わせていただくことになりました。
この場をお借りしまして、皆さまに深く感謝し、心からお礼申し上げます。
河南町のリーダーとして舵取りを行うという重大な仕事を担うということに大きな喜びを感じるとともに、将来を担う世代にまで持続可能なまちを築き上げていかなければならないという重大な責務に対し、改めてその重責に身の引き締まる思いであります。
はじめに、本年1月1日に石川県能登地方を震源とする最大震度7の大地震が発生し、甚大な被害を及ぼしました。この度の地震で、お亡くなりになられた方に、哀悼の意を表するとともに、被災されたすべての方々に、心よりお見舞い申し上げます。
そして、被災地の1日も早い復旧と復興をお祈りいたします。
さて、この4年間を思い返しますと、町長就任と同時期に新型コロナウイルス感染症が世界中に拡大したときでありました。
この未知のウイルスに対して、治療方法が確立されておらず、住民の皆さまが恐怖を感じる事態となりました。まさに、住民の皆さまと共に、新型コロナウイルスとの戦いの日々でありました。この間、生活支援や新型コロナワクチン接種などの各種施策を進めてまいりましたが、住民の皆さまには多大なご協力をいただき、この苦難を乗り越えることができました。そして、昨年の5月には、感染症法上の位置付けが2類から5類へ移行することとなりました。
新型コロナ対応につきましては、住民の皆さまのご協力に対し、改めて感謝申し上げます。
昨今の国際情勢をみますと、ロシアのウクライナ侵攻をはじめ、私たちに平和の大切さを改めて考えさせる出来事が発生しています。その紛争が食料やエネルギーの供給に混乱をもたらし、物価高騰による住民の皆さまの生活や町内の事業者などに大きな影響を与えております。
住民の皆さまの生活が、コロナ禍前に戻りつつある中、これらの対策にしっかりと取り組んでまいります。
また、昨年は、乗務員不足や乗客数の減少などにより、金剛自動車株式会社がバス事業廃止するという大きな衝撃が走りました。
地域のバスが廃止されることで、まるで、心の支えが突然消えたかのような喪失感を覚えました。当たり前に存在していたサービスが消えることで、私たちの日常がいかにその上で成り立っていたかを実感したところであります。
人口減少や少子高齢化の深刻な影響を痛感し、当たり前に提供されていたサービスが、今や当たり前ではなくなってきていることを、改めて認識した次第であります。
2014年に日本創生会議・人口減少問題検討分科会が公表したレポートでは、特に若年女性人口の減少によって、将来的な地方の消滅可能性が指摘され、本町も消滅可能性自治体とされました。
それから10年。本年4月24日に人口戦略会議が公表したレポートでは、本町は依然、消滅可能性自治体に変わりはありませんが、前回から若年女性人口の減少率が改善されました。
私は、人口が減少する時代にあって、「住みよいかなん みんなが輝くまちづくりを目指して」を念頭に、「住みやすいまちへ」「子育て・教育のまちへ」「まちの魅力、創造のまちへ」「住民サービスと行財政改革を推進するまちへ」の実現を住民の皆さまと一緒になって、進めてまいる決意であります。
1.住みやすいまちへ
近年は、地震災害や土砂災害、風水害など、全国各地で起こる数々の災害を目の当たりするにつれ、自然の驚異を改めて痛感させられます。
今後も気候変動の影響により、災害の更なる頻発化・激甚化が懸念される中、河川改修や急傾斜地崩壊対策などを通じて、減災対策を推進してまいります。
いつ訪れるともわからない自然災害の備えを平時から整えておくことが必要であります。大規模災害発生時には、自助・共助の観点が極めて重要であることから、タイムライン防災を推進し、地域の住民の皆さまがとるべき行動を定めたコミュニティタイムラインの策定や地域版ハザードマップの作成を支援してまいります。
災害への備えとして、地域住民のコミュニティ活動の中心的役割を果たす地区集会所について、避難所としての活用も踏まえ、改修を進めるとともに、今年度は防災倉庫の整備にも努めてまいります。
本年4月1日から、5市2町1村で構成する大阪南消防組合がスタートしました。消防広域化により消防力が強化されましたが、引き続き、消防・救急体制と地域に根差した消防団の充実に取り組んでまいります。
他市町村との境界や地区間などに防犯カメラの設置、地区が設置する防犯灯や防犯カメラに対する一部助成を実施いたします。地域における防犯ボランティア組織による青色回転灯防犯パトロールや見守り活動など、地域ぐるみの防犯対策への支援などの取組みを行ってまいります。
すべての世代が安心して幸せに暮らせる、持続可能なまちとするためには、高齢者の皆さまが安心して暮らせるよう、医療・介護サービスの充実に取り組んでまいりました。子育て世帯、高齢者や障がい者、生活困窮者などすべての住民の皆さまが地域社会の中で安心して暮らせるよう、町や社会福祉協議会などが中心となって、一人ひとりが豊かに安心して暮らせる地域共生社会に向け、重層的な支援体制の取り組みを進めてまいります。
先ほども述べましたが、新型コロナウイルス対策について、5類に移行したとはいえ、感染者が発生していることから、予防接種などその対策に努めてまいります。また、健康寿命の延伸を図るべく、国民健康保険では、30代からの特定健診を実施し、その他各種健診や保健指導などの体制整備に取り組んでまいります。
また、公共交通については、富田林市、太子町、河南町及び千早赤阪村の4市町村で構成する「地域公共交通活性化協議会」で検討を重ね、1日も途切れることなく、運行を開始することができました。ご協力とご理解をいただきました皆さまに、改めて、お礼申し上げます。
住民ニーズに応じた誰もが移動しやすい、住みやすい公共交通サービスを確立していくことは、乗務員不足への対応、運行経費に伴う財源の確保など、さまざまな課題が想定されますが、住民の生活活動を支援する持続可能なまちを目指して、新たなモビリティサービスの導入など、地域の活性化及び住民福祉の向上に寄与する公共交通の実現を目指してまいります。
住みやすいまちに向け、誰もが安心して楽しんで、日常の生活をできるまちづくりを進めてまいります。
2.子育て・教育のまちへ
少子高齢化が進行する日本において、子育てと教育の充実は、町の未来を支える重要な課題です。妊婦健診、子どもの健診の充実、第2子以降の保育料の無償化、幼児教育・保育施設における副食費の実質無償化、学校給食費の無償化など、引き続き、子育て世帯の経済的負担の軽減に努め、妊娠から出産、そして子育てに至るまで、切れ目ない伴走型支援に取り組んでまいります。
幼児教育・保育を一体的に行うこども園から小学校、中学校までの間、園と各学校のつながりをより重視して、子育て・教育の推進に努めてまいります。
また、ICT、AIを活用した教育環境の整備を進め、小・中学校においてはGIGAスクール構想により、児童・生徒の1人1台タブレットの整備を行いましたが、引き続き、子どもたちの情報教育を推進するため、ソフトなどを中心とした環境整備に努めてまいります。
子育て施策の充実に伴い、本町で住み続けたいと思っていただけるよう、子育て・教育環境の整備はもとより、給食費の完全無償化、子ども医療費の助成(22歳までのU-22医療費助成を含めて)、少人数学級の実施などにより、「子育て・教育は河南町で」という合言葉で取り組んでまいります。
また、グローバル社会を視野に入れて、英語に触れることができるさまざまな機会を提供することで、子どもたちの英語によるコミュニケーション能力向上を促進してまいります。
さらに、不登校児童・生徒が国や府の動向と同様に増加傾向にあることから、引き続き、教育支援センターを設置し対応しつつ、小・中学校に支援員を派遣し、校内での居場所づくりを行う出張型教育支援センターについて充実を図るとともに、不登校児童・生徒、いじめ問題、不適切な指導等への対応について、スクールロイヤー、臨床心理士、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー等の専門家を交えた学校支援チームの設置を引き続き行ってまいります。
近年、気温の上昇が続き、夏季の体育授業や学校行事において熱中症のリスクが高まっています。体育館の空調設備を整備することで、子どもたちが安全に活動できる環境を整え、これにより熱中症の予防はもちろんのこと、授業の質の向上につながるものと考えています。
さらに、体育館は災害時における避難所としての役割を果たします。
自然災害の増加に伴い、避難所の環境改善が急務となっています。空調設備を整備することで、避難生活を余儀なくされた方々が少しでも快適に過ごせるよう整備に取り組み、教育環境の向上と地域の安全確保に努めてまいります。
また、今年度からは小学5年生の授業において、間伐体験や森の散策、製材所見学、木工体験などの森林教育体験を通じて森から木材製品となる課程を学び、SDGs・森林・環境保全への関心を高める取り組みを実施してまいります。
子育て・教育のまちの実現に向け、子育て・教育は河南町で。子育て世代を応援するまちづくりを進めてまいります。
3.まちの魅力、創造のまちへ
本町の主要産業でもある農業は、遊休農地や農業の担い手不足などの課題に直面しています。
ほ場整備事業や土地改良事業、農業用水路の整備を通じて、機械化が進み、作業の負担軽減がされるなど、生産性向上を図り、持続可能な農業を実現してまいります。
新たな就農者への支援のほか、高収益化、道の駅かなんを介した販売などに力を注いでまいります。
そのためにも、道の駅活性化施策を進めていかなければなりません。民間事業者との連携を深め、賑わいの創出に向けて検討してまいります。
また、今年度は農業経営基盤強化促進法による、将来の農地利用の姿を示す地域計画の策定を行ってまいります。
地域の産業、特に商業の振興においては、電子地域通貨「カナちゃんコイン」を通じて、還元キャンペーンやATMチャージキャンペーンなどを実施し、住民や事業者の皆さまに幅広い支援策を実施してまいりました。
急激な物価高騰等も踏まえ、地域の経済循環による町の活性化を目指すためにも、地域通貨事業を引き続き行ってまいります。この事業により、物価高騰による住民の生活支援にもつながるものと考えております。
高度経済成長期、人口の増加や住民ニーズなどに対応するため公共施設の整備を進めてまいりました。これらの施設は、当時の町の発展と住民の生活向上に大きく寄与してきたものでありますが、施設の老朽化と人口減少という新たな課題を解決すべく公共施設再編整備基本計画を策定し、施設の再編に取り組んでまいりました。
再編整備計画により役割を終えた施設については、その空間を再編し、利活用を進めることにより、跡地を含めたまちの再生や活性化につなげていけるよう賑わいの創出に努めてまいります。
まちの活性化や賑わいの創出に向けて、道路交通網の整備は大きな課題であります。
災害時において緊急輸送路となりうる大阪南部高速道路の役割は、地域の発展と命の道として、関係機関と連携して、早期実現に向け、働きかけてまいります。
また、主要地方道柏原駒ヶ谷千早赤阪線(山城バイパス)の整備を促進するとともに、生活道路や公共下水道の整備を進め、快適な生活、住んでよかったと思えるまちづくりを進めてまいります。
次に、私たちが生活を営むこの地球の温暖化に対応して、本町においても、ゼロカーボンシティ宣言をいたしました。「河南町脱炭素ロードマップ」に基づき、本町においても2050年までにカーボンニュートラルを目指し、住民の皆さまへの啓発活動を行うほか、電気自動車の普及促進を図るため、充電設備の補助や公用車の電動車化などを進めてまいります。
まちの魅力を創造し、みんなが生涯にわたって活躍できるまちづくりを進める必要があります。住民の皆さまの文化創造力を高めるための公民館活動や図書館などの充実に努めてまいります。
また、本年は第33回オリンピック競技大会がフランスのパリで開催されます。世界が注目するスポーツの祭典であり、スポーツ熱が一層高まるものと考えられます。スポーツを通じて、生涯にわたり、健康で長生きできる社会の実現に取り組んでまいります。
さらに、来年には、大阪・関西万博が開催され、世界中から注目を集めることが予想されます。インバウンドでの来場者も多数見込まれ、地域経済の活性化に大きな役割を果たすことが期待されています。本町においても、万博に向けた機運を高めるため、さまざまなイベントやPR活動を通じて、機運醸成を図ってまいります。
まちの魅力、創造のまちを実現するため、まちをかたちづくる基盤整備、そして新たな文化を創出するまちづくりを進めてまいります。
4.住民サービスと行財政改革を推進するまちへ
デジタル化は、現代社会において、ますます重要なテーマとなっており、私たちの生活やビジネス、行政サービスに多大な影響を与えています。
デジタル技術を活用することで、行政手続きの簡素化と迅速化を図り、住民の皆さまに対するサービスをより効率的なものとするため、スマート窓口の体制整備を進めてまいります。
また、統合型GIS(地理情報システム)を導入し、地理空間情報である都市計画や防災情報(ハザードマップ)などを一元管理することで、行政サービスの効率化を図り、パソコンや携帯端末等で必要な情報が入手できる仕組みを構築してまいります。
人口減少社会において、先ほども述べさせていただきましたが、消滅可能性自治体となっていることから、持続可能なまちを形成するためにも、財政の健全化、行財政改革を推進してまいります。さらに、2町1村で設置しております基礎自治体の将来のあり方を考える「2町1村未来協議会」において、課題への対応方策の検討、将来のあり方について、議論を深めてまいります。
住民サービスと行財政改革を推進するまちの実現に向けて、デジタルの活用によるサービスの向上と持続可能なまちづくりを進めてまいります。
以上、私の基本的な姿勢と、今年度において推進しようとする主要な施策の一端をご説明いたしました。
今後4年間におきまして、「住みよいかなん みんなが輝くまちづくり」の実現に向け、鋭意、創造性を発揮しつつ、まちづくりの諸課題に取り組んでまいりますので、住民の皆さま並びに町議会議員の皆さまのより一層のご理解とご支援をお願い申し上げ、2期目の所信表明とさせていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
政策総務部 まちづくり秘書課
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:210・211・213・215)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール/秘書企画係:hisho@town.kanan.osaka.jp
Eメール/広報担当:kouhou@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム






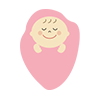

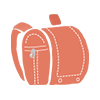

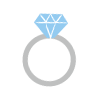

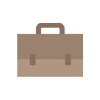

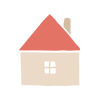



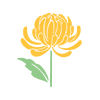

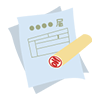





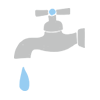
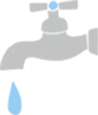
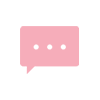


















更新日:2024年06月04日